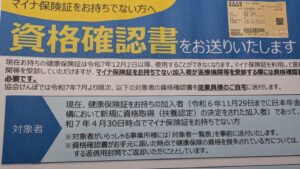育児・介護休業法が改正されました
段階的に今年4月に改正があったところですが、10月1日付で以下のことも会社に義務付けられました。
ⓐ柔軟な働き方を実現するための措置🐤
育児による時短制度は、基本的にお子さんが3歳になるまでの間が対象です。
3歳を迎えた後の育児と仕事の両立支援として、新たな制度が設けられます。
何をするべき?
事業所は、次の5つのうち、2つ以上を選び、就業規則等で定めておきます。
対象従業員は、そのうち1つを利用できます。
①フレックスタイムや時差出勤により、始業時刻等をずらす
②月に10日以上利用できるテレワーク等の導入
③保育施設の設置運営等
④年10日以上利用できる養育両立支援休暇の付与
⑤時短勤務制度
対象従業員は?
3歳以上小学校就学前のお子さんを養育されている従業員です。
※協定締結により、入社1年未満の方や週の所定労働日数が2日以下の方など、対象外とされることもあります。
定めさえしておけば十分?
職種や業務内容により、従業員が選択したくても選択できないような措置もあるでしょう。
「労働者の職種や配置等から利用できないことがあらかじめ想定できるものを措置することは、事業主が措置義務を果たしたことにはなりません」とされています(「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」Q2-5より)。
また、選択にあたっては、過半数組合または過半数代表者からの意見を聴くこととされています。
さらに、3歳未満のお子さんを養育されている従業員に対して、個別にお知らせ・意向確認が必要です。
ⓑ仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮🐤
従業員が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき、会社は育休制度等について個別に周知、意向確認をすることとなっています。
10月からはそれに加えて、勤務時間、勤務場所、業務量などについても個別に意向を聴き、それに対し、自社の状況に応じて配慮することとなりました。
上記ⓐの3歳未満のお子さんを養育されている従業員にも同様に、意向を聴き、配慮する必要があります。
「お子さんが何歳のときに、どのような制度を利用できるのか……?」
従業員の方へのフォローが難しいなと感じましたら、ぜひ社労士事務所をご活用ください。